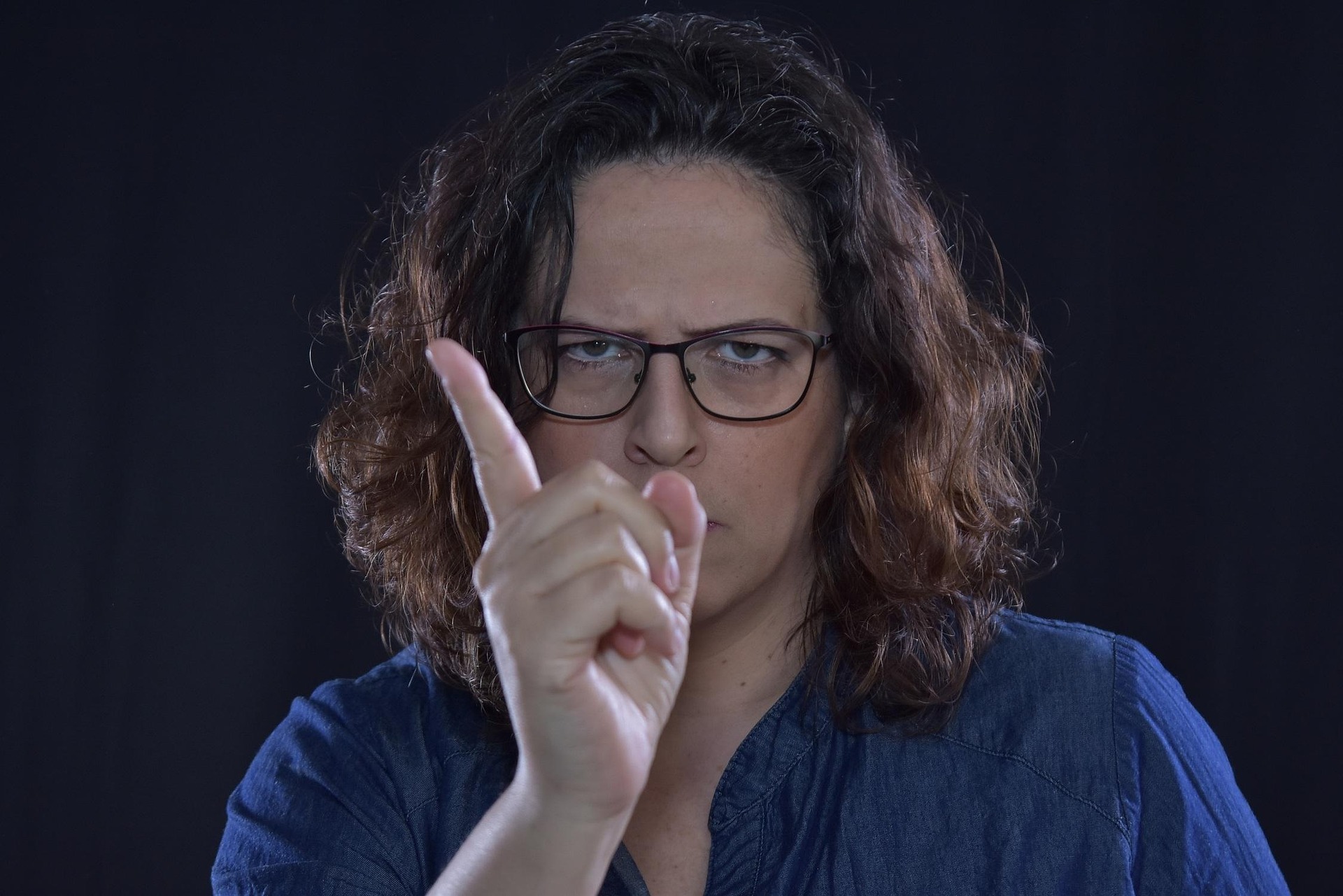こんにちは。矢田の丘相談室カウンセラーの田中剛です。プロフィールはこちら。
依存症の本人はどうして平気で嘘をつくんですか?と
質問を受けることがよくあります。
例えば、アルコール依存症では、
酒を隠して飲み、明白に飲んでいるのに、
「飲んでいない」
と本人が嘘をつくことが発生しがちです。
家族からすると
「どうしてまた噓をつくのか」と
腹立たしく思うでしょうし、
隠して飲むから、本人を信用できなくなっていきますよね。
事例を通して、考えてみましょう。
なぜすぐばれる嘘をつくの⁈
主治医の先生の前では飲んでいないと言っている。
けれど、部屋に酒瓶が転がっていたし、しょっちゅう酒臭い。
明らかに様子がおかしいから「また飲んだでしょ?」と聞くと
「飲んでない」と嘘をつく。
「どうして嘘をつくの?」と追求すると、
「うるさい!」と怒って部屋に閉じこもる。
本人の体が心配と言うことももちろんあるけど、
あんなに大変な迷惑を家族にかけたのに、
どうしてまだ酒を飲んでいるのか?なぜ家族を欺くのか?と
言う怒りの方が強いです。
嘘をつく原因①「報酬欠乏症」
この事例のように、すぐばれるような嘘を繰り返されると、
本当に疲れてしまいますよね。
では、どうして依存症の本人は嘘をつくのでしょうか?
家族を欺きたいのでしょうか?
そこには、依存症特有の脳の変化が、実は関係しています。
アルコール依存症は、
耐性上昇(体が酒に慣れてしまう)や
疑似ホメオスタシス(アルコール血中濃度を保とうとする体の働き)などの
さまざまなメカニズムによって成立していますが、
依存症本人の嘘には、
「報酬欠乏症」
という脳の変化が
関係していると思われます。
報酬欠乏症は、アルコールだけでなく
多くの依存症で、共通する病理です。
報酬欠乏症とは脳の快感を感じる部分が変わってしまう、
依存症の中核病理の一つです。
最初は酔っ払って気持ちよかった(快感があった)のに、
報酬欠乏症が進行すると、
次第に酔っぱらっているときが普通(快感に慣れすぎて普通)になり、
しらふの時間が耐えがたく苦痛になるという
感じ方の変化(報酬系の変化)を起こします。
したがって、飲みたくて飲むのではなく、
苦痛を低減するために再飲酒せざるを得ないようになってしまうのです。
脳の命令に逆らえずに飲むのです。
逆らい難い脳の命令により、飲まずにいられない、
でも家族とは飲まないと約束してしまった→隠れて飲む、となるわけです。
脳と、本人の意思が、
逆を向いてしまうから必然的に嘘になります。
嘘は依存症の症状と言われるゆえんです。
嘘をつく原因②「両価性」
報酬欠乏症が招く、このような
「飲みたくないのに飲んでしまって結果として嘘になってしまう」
依存症本人の心理状態を
「両価性」と言います。
この両価性も、多くの依存症に、
共通してみられる病理です。
飲みたい脳と、飲みたくない本人が同時にいるような状態です。
右を向けと言うと、左を向きたくなるような状態です。
この両価性があるために、
嘘を追及すれば、逆にもっと嘘をつくようになります。
本人に飲酒を反省させようとすると、
飲酒欲求が高まります。
でも、家族は飲酒の悪を自覚させたい!
この悪循環なんです。
だからどんどん嘘をつくようになるんですね。
これは依存症の脳がもたらす症状なのです。
家族が嘘を暴きたいのは、依存行動による傷付きを防止したいから
一方で、ご家族が本人の嘘を追及したいのは
家族としては、本人に既に対応しつくしていて、
もう二度とあんな酷い思いはごめんだ、と
過去のトラウマを回避したいから、嘘を暴きたくなり、
本人を責めたくなるのです。
これはトラウマによる、トラウマ回避の効果です。
でも、依存症の病理から考えると
悲しいことに、逆効果の対応なんです。
家族が、本人から受けたトラウマが原因で、
依存症を悪化させる対応を繰り返してしまう、悪循環なのです。
それではどうすれば良いのでしょうか?
家族のトラウマを癒して、両価性を活かして関わる!
そこでご家族に必要なのは、
家族自身が本人の飲酒等の依存症によって
傷ついた体験を癒すことで
トラウマ回避の悪循環から逃れ、
戦略的に両価性を刺激しない対応に切り替えられるようになる
ことが有効なのです。
家族が本人の依存症行動によって
傷ついた体験を癒すことで、
嫌悪・恐怖の記憶(トラウマ)が軽減され、
「飲むか飲まないかはあなたに任せます」、
といった、心理的境界線を守った対応ができるようになります。
(心理的境界線についてはこちらもどうぞ)
このような対応をすると、両価性の原理から
「飲まない方が良いかもしれない」と本人が考える可能性が高まるのです。
(右を向けと言うと左を向くから)
また、嘘を暴かなくなることで
本人が正直に話してくれるようになる可能性も
高まるでしょう。
さらに、家族がトラウマを癒すことで
CRAFTや動機付け面接等の家族対応テクニックを
戦略的・表面的な演技として使えるようになります。
表面的な演技で全然構いません!
これは、家族のメリットのための戦略です。
そのおまけとして、本人の回復にも役立ちます。
家族会や、カウンセリングは、ご家族のためにある
癒すためには、家族会で怒りを吐き出すでもいいですし、
カウンセリングルームでケアを受ける、でもいいでしょう。
依存症に詳しいカウンセリングルームなら、
同時に戦略的対応もコーチングしてくれて、一石二鳥です。
ちなみに家族が家族相談に繋がってる本人の方が、
回復率が高いことはさまざまな研究で分かってきています。
また、本人が依存症行動の問題に気付くのは、
依存行動を止めた後であることも研究から明らかになってきています。
依存症を止めるのに、問題に気付かせる必要は無いんですね。
当相談室では、上記のような、ご家族に対するCRAFTなどの
個別家族相談が可能です。
また、ご本人に対する、認知行動療法等の
依存症面談も可能になっております。
どうぞご相談をご検討ください。
ご相談・ご予約はこちら。
※事例は全て架空事例です。複製・転載は固くお断りします。
※ご本人の状態によっては、ケースに応じて、別の対応が必要になることがあります。